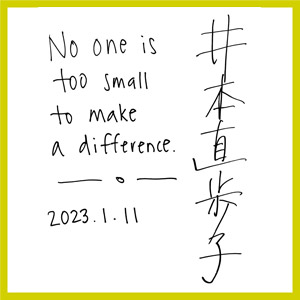MENU
三洋化成ニュース No.539
2023.07.12

オリンピック競泳選手として活躍後、国連児童基金(ユニセフ)職員として途上国の国際貢献活動を行い、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)を迎えるにあたってはジェンダー平等推進チームのアドバイザーとして活動された、井本直歩子さん。
東京2020大会は、史上初めて、ジェンダーステレオタイプに真正面から取り組んだ大会となりました。多様な人々が自分らしく生きられる社会を実現するために、大切なことは何か、井本さんのお考えをお聞きしました。
-- 発展途上国に関心を持ったのは、いつ頃ですか。
競泳選手時代です。私たち日本代表選手には、国際大会に出るたびに、日本オリンピック委員会(JOC)や水泳連盟、スポンサー企業などからたくさんの支給品があるんです。水着や帽子、ユニフォームにスーツにジャージに靴と、スーツケースいっぱいに、大会ごとにいただいていました。片や、途上国の選手は満足にゴーグルもつけずに出場している。「こんなに恵まれている自分と、そうでない選手が、同じスタートラインで競っていいんだろうか」と、物質的な不平等に罪悪感を持ちました。
-- スタートラインに立つ前に、そこまでの差があるのですね。
選手村の食堂に行くと、途上国の選手がお菓子をたくさん食べていました。いつもどんなものを食べているんだろう、私たちは体調や栄養に気を付けて食べているけれど、そういった知識を得る機会もなかったのかな、と思いました。内戦中のボスニア・ヘルツェゴビナの選手が、地雷を避けるために場所を移してトレーニングを行い出場したという話を聞く機会がありましたし、高校3年生だった1994年にはルワンダ大虐殺が起こり、約80万人が素手で殺害されるという新聞記事を読んでいました。私がアジア大会に向けてトレーニングをしている時に、地球の裏側でこんなことが起こっている。大きな矛盾を感じ、いても立ってもいられない気持ちになりました。
-- 国際大会を通して、日本と途上国の格差に気付かれたんですね。
はい。大学受験を控えて将来のことを考えるなかで、途上国の人のために働きたい、国連で紛争予防に関わりたいと思うようになりました。当時水泳の選手生命は、10代がピークといわれていたので、引退後にどんな仕事をしたいか、自然と考えていたんです。
-- アスリートの方は、引退した後もスポーツに関わる方が多いように思っていました。
私はすごく欲張りで、何でもかんでも手に入れたくなってしまうんです(笑)。水泳では、オリンピックに絶対出るぞと思ってがんばってきましたが、同時にその後の人生のことも考えて選択肢を持っておきたいと思いました。学ぶのは楽しかったです。
-- 1996年、アトランタ・オリンピック出場を果たし、女子800メートルのリレーで4位に入賞されていますね。
アトランタは私にとって最初で最後の大会になると思って臨んだものの、個人種目では予選落ち。帰りの飛行機で号泣していたところ、冬夏合わせて7回のオリンピックに出られた橋本聖子さんが「満足していないなら、1回であきらめちゃいけない」と声をかけてくださいました。現役続行を決意し、心機一転してアメリカに留学したのですが、アメリカの大学では勉強もきちんとしないと大会に出られないんです。学業と競技の両立は必然でした。残念ながら2度目のオリンピック出場はかないませんでしたが、1年1年練習を積み重ねて、現役最後のレースとなった代表選考会では全種目で自己ベストを更新できたので、未練はありませんでした。
-- 引退後は、国際関係の仕事という夢へ向かわれたのですね。
イギリスの大学院の貧困・紛争・復興コースで学び、その後、国際協力機構(JICA)でガーナ、シエラレオネ、ケニア、ルワンダに赴いて現場経験を積みました。30歳の時、国連児童基金(ユニセフ)職員の試験に合格することができました。
-- ユニセフ職員として、どんなお仕事をされたのでしょうか。
最初に派遣されたのは、スリランカの教育部門。教育は子どもの成長にも平和構築にも欠かせませんから、この分野を自分の専門にできたのはラッキーでした。JICA時代にはできなかった紛争の第一線で活動をすることができてうれしかったです。
当時はスリランカ北部で紛争があり、人々が国軍に追いやられて、10万人規模の国内避難民のキャンプができていたんです。そのなかで仮設教室を作って、毎日飛び回っていました。心のケアの一環として、プログラムにスポーツを盛り込んだこともありましたよ。ボールを追いかけてだんだんと笑顔になっていく子どもたちを見て、スポーツの底力を感じましたね。
-- 過酷な地域で危ない目に遭われませんでしたか。
2010年のハイチの大地震後に現地で復興支援に携わった時はテント生活でしたが、普段はユニセフが職員の住環境やセキュリティを整備して職員を守ってくれます。危険なことはほとんどなく、本当に毎日、楽しいんですよ。ほかにフィリピン、マリ、ギリシャでも活動しました。

-- ユニセフ時代を経て、東京2020組織委員会ジェンダー平等推進チームのアドバイザーに就任されたんですね。
ユニセフに入って14年ほど経ち、ちょうど契約が切れたタイミングで休職して、自分の家族やパートナーと過ごす時間を取ったり、一度立ち止まってみたりしたいなと。2021年1月に帰国すると、テレビで組織委員会の森喜朗会長の女性蔑視発言問題を知りました。
私にも取材が来てしばらく騒がれていたんですが、そのうち「年配の方だから、仕方ない」という感じで、だんだん落ち着いてきて。
でも、私は「これで終わらせてはダメだ」と思ったんです。声を上げ続けて、現状を変えるために行動しなければいけない、スポーツ界や国際機関に長く所属してきた経験を生かせればと思いました。ちょうど組織委員会にジェンダー平等推進チームが発足したと聞き、リーダーの小谷実可子さんにつなげてもらい、お手伝いさせてくださいと言いました。
-- チーム発足は、国内外での批判を受けて、組織として改善の姿勢を見せるためということですね。
そうです。大会までの短期間に実行する施策と、継続的に行っていく施策を整理して発表することになりましたが、一般の方に伝わるような変化も起こしたいと思い、報道に関するジェンダーステレオタイプを取り除くことに着手しました。すでに国際オリンピック委員会(IOC)がメディア向けのガイドラインを作っていましたが、日本ならではの問題も取り上げる必要があると思ったんです。
-- IOCのガイドラインについて教えてください。
スポーツの報道において、男らしさや女らしさの偏見をなくし、ルッキズム偏重報道にも配慮し、スポーツをありのまま伝えることにより、スポーツ界のジェンダー差別をなくしていくためのガイドラインです。
日本のスポーツ界では「美女アスリート」「イケメンアスリート」など、顔形のいい選手が競技の成績のいい選手よりも注目を集めることがありますよね。また、スポーツ雑誌では、男性アスリートはトレーニング風景や試合のショットが取り上げられるのに、女性アスリートはかわいらしい私服を着てプライベートの話を聞かれがちなんですよ。「ママさんアスリート」などもそうですが、競技の本質とずれた話題が多く取り上げられているんです。
-- 報道の仕方によっては、古い価値観を再生産してしまうことになりかねないですね。
そうなんです。選手自身も、そのような取り上げ方を望んでいないかもしれません。読者や視聴者も、選手のプライベートより競技のことを知りたいかもしれない。
女子スポーツにとっても、顔形のいい選手ばかり取り上げられれば、スポーツの本質の魅力を狭めます。女子のスポーツを実際に観戦すると、迫力があってとてもかっこいいんです。ありのままのスポーツの魅力がメディアを通して伝われば、「女らしさ」の偏見が弱まり、多様なかっこいい女性のイメージが定着すると期待しています。
-- 選手の容姿やプライベートの話をきっかけに競技も注目される、ということもあるでしょうが、それでは競技の本質的な魅力は伝わらないということですね。
はい。選手の容姿やプライベートは話題にはなりますが、ただの一過性のブームにしかなりません。また、選手たちも「競技が注目されるためだから」と言われると、嫌な取り上げ方をされても我慢してしまうんです。スポーツ界の無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)は根深く、メディアやスポーツ関係者、視聴者やファンなど、みんなが一緒に考え、対話しながら動かないと解決しない問題だと強く感じました。
-- 海外メディアでは、アスリートをどのように取り上げているのですか。
海外で、アスリートのプライベートを報じているのはゴシップ誌くらいです。もちろん外見よりも実力に基づいて報じられるほか、IOCのガイドラインにのっとって、チーム競技ではスター選手ばかりではなく、全ての選手をバランスよく取り上げるように、配慮されているように感じます。
-- 日本とはずいぶん違いますね。
そうですね。2022年に、南ア共和国の放送局のサッカーW杯中継を見ていたら、専門家の女性が解説者として出ていて、とてもわかりやすく解説していました。考えてみれば、男子サッカーを男性だけが解説しなければならない理由はないですもんね。その大会では日本人女性が審判をしましたし、ドイツ対コスタリカ戦はサッカーW杯史上初めて、ピッチ上の審判が全員女性でした。経験が長いメンバーがそろい、とてもいい采配だったと思います。スポーツには見ている人の固定観念を打ち破る力があり、注目が集まる国際的な大会を利用して、固定観念を打ち消す機会にしていく力があることを考えさせられました。
-- 日本でスポーツ番組に登場する女性は、アシスタントの役割であることが多いと感じます。解説や実況がうまい人も、きっといるはずですよね。
男子サッカーの試合をなでしこジャパンの選手が解説する番組もあっていいと思います。「女性だから」「男性だから」という理由でできないことは、限られています。メディアにはそのようなステレオタイプを崩してもらいたいと思っているんです。

ハイチ大地震後にユニセフの支援で建てた仮設教室にて
-- 多様性が尊重される社会に向けて、私たちはどのようなことに気を付けるべきでしょうか。
まずは自分のなかで「おかしいな」と思うことを口に出すことだと思います。例えば結婚している女性なら、配偶者のことを「主人」と言うのをやめるとか。「嫁」「家内」も家父長制的で、今の時代にはそぐわない。
-- 自分の配偶者を「主人」「嫁」と呼ぶことはやめられるものの、他人の配偶者のことを「ご主人」「奥様」以外の呼び方をするのが、なかなか難かしいんです。「パートナー」「お連れ合い」という言葉もありますが、世間に浸透しているとはいい難い。使い慣れた言葉にも、実はおかしなところがあるから、こう変えていきませんか、と提案していくことも大事ですね。
その通りです。子どもに対しても「男の子なんだから泣くな」とか「行儀よくしないと、お嫁にいけなくなるよ」など、よく言われますよね。「そういう言葉は最近、使わないんですよ」と、年上の方や目上の方にもきちんとお話しする勇気を出せるかどうかは悩むところです。そういう発言をした人がいれば、後で二人になったときにそっと伝えるとか。「『細かいことにうるさい人だ』と思われたくない」という気持ちもわかりますし、ものすごく社会的地位の高い方に伝えるのは勇気がいりますが、今の状態を後世に引き継いではいけないと変革の側に立つ勇気が必要ではないでしょうか。
-- そうですね。逆に、自分が指摘される立場になることもあるかもしれません。
そうなんです。私も勉強しているつもりですが、まだまだ足りていないですし、自分が無意識のうちに持っているステレオタイプにふと気付くことが、今でもよくあります。でも、それは決して恥ずかしいことではないと思います。家庭でも、ご家族と時代錯誤な言葉遣いやステレオタイプな物の見方について話すことは、とても大きなことへの小さな一歩だと思います。間違っても直せばいい、失敗したら反省すればいいという社会にしていきたいですね。
-- 指摘されたら、感謝の気持ちで受け入れることが大切ですね。一方で「あれもこれも差別だと言われたら、何も言えなくなってしまう」と感じる人もいるのでは。
確かに「うかつにものを言えない」という恐怖を取り除くことは大切です。ダイバーシティは、その人らしさを大事にすることが原点。受け取った側が嫌だと思うかどうかがハラスメントの境目。同じ発言でも、当事者どうしの関係性によって感じ方は違うんです。女だから男だからという固定観念で判断するのではなくて、その人らしさを見る。それが自分の固定観念を崩すことにもつながり、誰もが自分らしくいられるような社会につながると思います。
ジェンダーの問題は女性だけの問題ではなく、男性にも大きく影響しています。女性は「料理や家事が得意」というステレオタイプに苦しめられてきましたが、男性も「稼がなければ」「家族を守らなければ」などのステレオタイプを押し付けられて、苦しんできた人もいると思うんです。

一般社団法人SDGs in Sports主催の「女性リーダーサポートネットワーク
Think Together, Change Together」の活動(画面最上段左端が井本さん)
-- 井本さんは今後どのような活動をしていかれるのでしょうか。
私が今、力を入れているのがガバナンスのなかのジェンダー平等です。どんな組織でも、30%ほどの多様性がないと、組織が硬直化してしまうといわれています。とりわけ、日本はこれまで、男性中心の社会構造で、年功序列で一部の人が意思決定をしていたり、その判断に誰も意見が言えなかったりという状況です。それを打ち破るためには、例えば女性などの異質な人が30%以上必要です。
組織内の議論を活発化させて、より良い決断をどんどんしていくためには、トップが多様でなければいけない。「女性がいると会議が長くなる」というのは、今まで男性も含めてみんな発言したかったけれど、我慢していたから会議が短かったということでしょう。
-- 「それ、おかしくないですか」と声を上げる人が一人二人ではなく、30%になれば、変わってくるということですね。
特に、若い人や女性はなかなか自由に発言しにくいと思いますが、企業においても発言できる文化をつくることが大切ですね。もっと未来志向で将来を見据えた議論をして、トップ層のダイバーシティに取り組めば、政治や企業など、日本の社会の決断がどんどん変わっていくと思います。ちょっとずつ変わっていけば10年後の日本はたぶん相当違っているでしょう。
-- 女性やマイノリティだけのためではなくて、みんなが生きやすくなる社会になってほしいです。本日は、ありがとうございました。
と き:2023年1月11日
と こ ろ:西新橋・当社東京支社にて